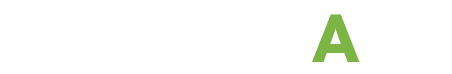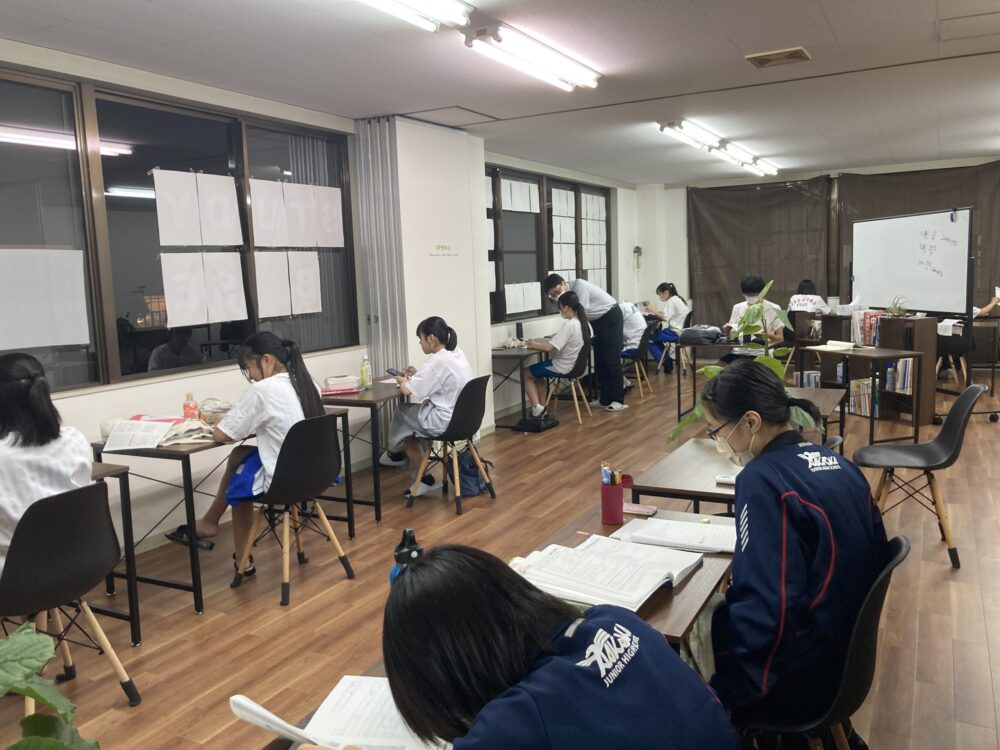夏休み明けのテストが終わりました。
これからどんどん、答案用紙が返却されます。
そこで改めて思ったことは「問題を解く順番に難あり」ということです。
どの科目でもいえることですが、問題を解く順番に少し気を付けるだけで、もう少し点数につながることはあります。
大事なこととしては、「わからない問題はとりあえず飛ばしてしまうこと」です。
誤った解釈をしていることがある
時折、誤った解釈をしている生徒がいます。
テストの問題が進むにつれ、問題の難易度が上がっていくと考えているパターンです。
たとえばテスト全体で大問が①~⑧まであったとします。
①が一番簡単で⑧が一番難しいと思っている生徒がいますが、決してそのようなことはありません。
大問⑧でも簡単な問題が出題されていることは普通にあります。
難易度はバラバラ
大問が①~⑧まであったとします。
それぞれの中にも小問が設定されています。
たとえば③の中の問題1、問題2、問題3、④の中の問題1、問題2といった具合です。
その場合、問題1が簡単で問題2が難しくなっているケースがあります。しかしこれもケースバイケースです。
ただ思い込まないでほしいのは、先ほどの大問の件でも話しましたが、大問⑧が特別難しいというわけではなかったり、大問⑧でも問題1の難易度は低く、問題3の難易度が高いといったケースがあるということです。
つまりどこの問題においても、簡単な問題を難しい問題が散りばめられているということです。
わからない問題はまずは飛ばす
以上のことを踏まえ、わからない問題があった時にはどんどん飛ばすこともテストの点数を少しでも高めるテクニックとなります。
たとえば今年の中学3年生の学力調査テストの英語ですが、一番最後の問題は英作文でした。
その前の大問は条件作文でした。
さて、このうちどちらが解きやすいかというと、一番最後の英作文です。
というのも、英作文は自分の好きに英文を作ってよいためです。
条件作文の場合は、条件が設定されており、その範囲内で回答するといった制限が付きます。
そして英作文の場合、特別難しいことを書こうとしないほうがよいです。基礎的な英文法で何とかなります。
まず主語と動詞を気を付けます。その次に時制を気を付けます。
さらに怪しい単語は使用せず、自分が間違いなくわかる単語を使うようにします。
文章の内容が極端な話ウソでも構いません。英文法として成り立っていればよいのです。
学力調査テストに関しては、また別の記事でお話していきたいと思いますが、今回のテストでうまくいかなかった人は、問題の解く順番をもう少し意識してみるとよいかもしれません。
少なくても1つの問題に固執することはやめたほうがよいでしょう。
あまりに1つの問題に時間がかかるのであれば、そのほかの問題を見直しする時間に割り当てたほうがよいという時もあります。